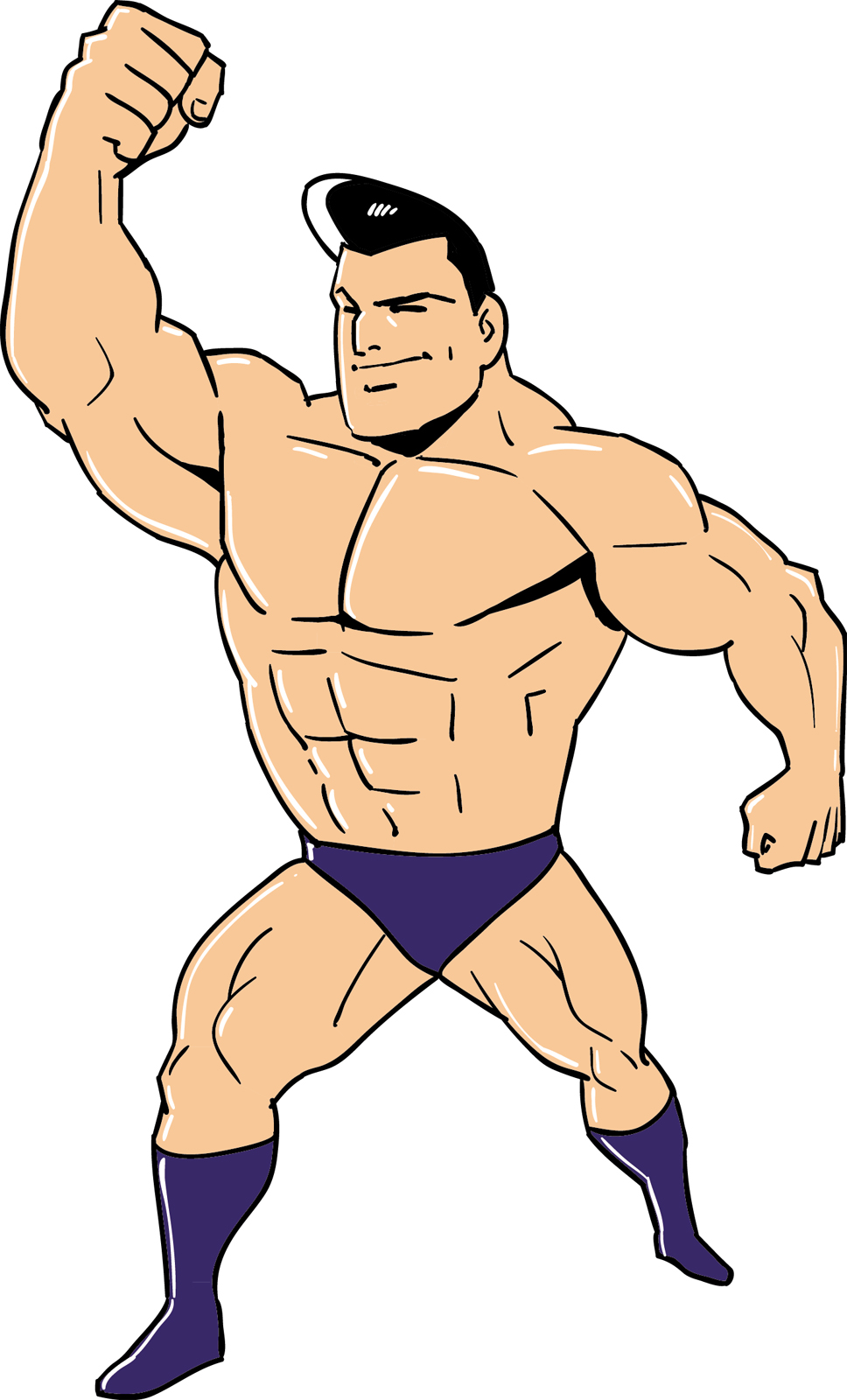おはようございます。
役員の井尻です。
本日は固定筋・共同筋・弛緩です。
言葉の定義にはなると思いますが正確に説明できますか?
説明できない方はぜひご覧ください。
固定筋・安定筋
静止性収縮によって骨や体の部分を固定して支持を与える。
腕立て伏せの姿勢では頭部が重力方向に下がらないように頸部伸筋群は静止性収縮を行っている。
共同筋
広い意味ではひとつの運動に参加するすべての筋である。
とくに中和筋としての機能は重要である。支援共同筋は動筋による不必要な動きを抑制しあうものである。
2つの筋が1関節に対して同じ働きをするとき、ほかの働きが拮抗して不要な運動を中和する。
左右腹筋は脊柱屈曲運動のさいにこのような働きをする。
外腹斜筋は屈筋として動筋になり、体幹の回旋運動については左右が拮抗して中和する。
2~多関節筋が短縮するとき、中間関節の運動を防止するために別の筋が静止性収縮を行う。
これを真正共同筋という。
手関節が伸展位に保持されなければ、手指屈筋は十分な機能を果たせない。
弛緩
筋の弛緩は筋の収縮がない状態である。完全に筋が弛緩しても、筋の物理化学的性質による弾力、刺激に対する神経・筋の反応などによって、筋には一定の緊張がある。これをトーヌスという
筋緊張については後日記載します。
<まとめ>
臨床的には固定筋が重要かと思います。特に体幹が固定筋に働くことが多く、その低下で動作に支障がみられます。
コアなどのトレーニングは固定筋として必要ですよね。