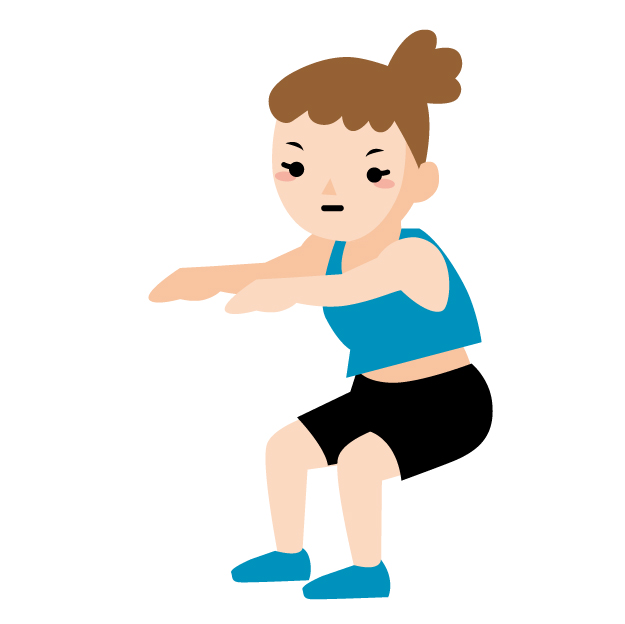おはようございます。
役員の井尻です。
寒い時期に勉強していると国家試験の勉強をしていたことを思い出します。
朝から夜まで勉強漬けで問題集や参考書とにらめっこしていた時期が懐かしいですね。
前日にお酒を飲んだことはいい思い出ですが…
さて、本日は筋の働きについてです。
働きには大きくわけて2つあります。運動方向別では5つあります。
基本的な部分ですが、復習としてご覧ください。
筋の働きは収縮と弛緩である。
解剖学的には筋が収縮しているに起こる運動方向によって、筋の働きを分類する
①屈筋:1軸性関節で両骨間の角度を0°に近づける。
②伸筋:屈筋の反対の働きで、両骨間の角度を180°に近づける。
③内転筋:四肢を体幹に近づける。
④外転筋:四肢を体幹から遠ざける。
⑤回旋筋:四肢や体幹をその長軸に沿って回旋させる。
この他には括約筋、散大筋、挙筋、下制筋などがある。
運動学では四肢や体幹の目的運動、協調運動が問題となる。そのために筋の動きについて、求心性収縮だけでなく、遠心性収縮、静止性収縮、弛緩などの分類がなされる。
これの区分は運動分析を行ううえで重要である。
<まとめ>
収縮と弛緩という分類で簡単ですが、臨床ではこの働きができない方がほとんどですね。
もちろん、中枢神経や筋緊張など様々なことがふくまれますが…包括的に考えること難しいですね。