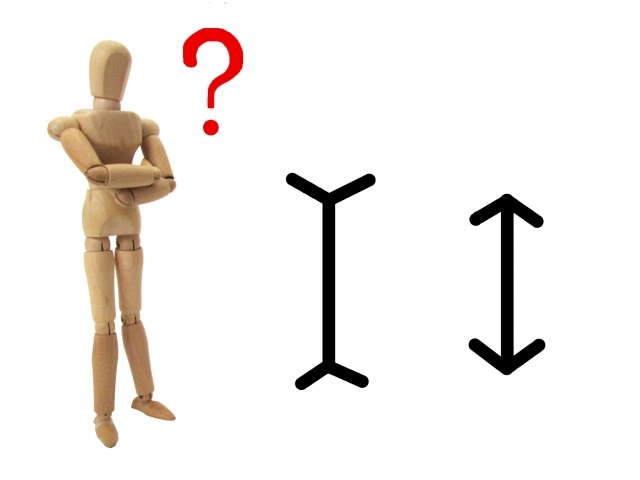おはようございます。
役員の井尻です。
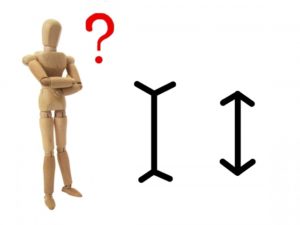
9月は連休が多いですね。
と言っても私自身は働いていることが多いですが…
また、10月からアドバンスコースAの開始がありますので準備もしっかりしていますよ!
もちろん、ベーシックコースも随時募集しておりますので気軽にご参加ください。
今回は胸郭可動性・胸部X線についてまとめます。
酸素飽和度と呼吸困難感評価スケールも要な評価ですが、以前UPしていますのでそちらをごらんください。
胸郭可動性
巻尺を用いた胸郭の周径測定が臨床においてはよく用いられてる。
①上部:腋窩部
②中部:剣状突起部
③下部:第12肋骨下部
の三か所の安静呼気を基準にして安静吸気位・最大呼気位および最大吸気位の周径差をみる。
※正常値は健常人で3~7cm、呼吸不全患者で2~5cm程度が平均である。
胸部X線所見
体位排痰法の施行後には有用な情報がえられる。
また、肺や気管の状態を正確に把握するにも胸部X線写真が最も正確である。
①骨性胸郭:肋骨・鎖骨などの高さ、走行の左右対称性
②横隔膜:高さ、心横隔膜角、肋骨横隔膜角
③中央陰影:心胸郭比など
④両肺野:異常陰影、透過度の増加など
【まとめ】
胸郭可動性も評価として認知・覚醒度がしっかりしていれば有用なテストです。
X線は透過性はもちろんさまざまな情報が得られるためみておいても損はないと思います。