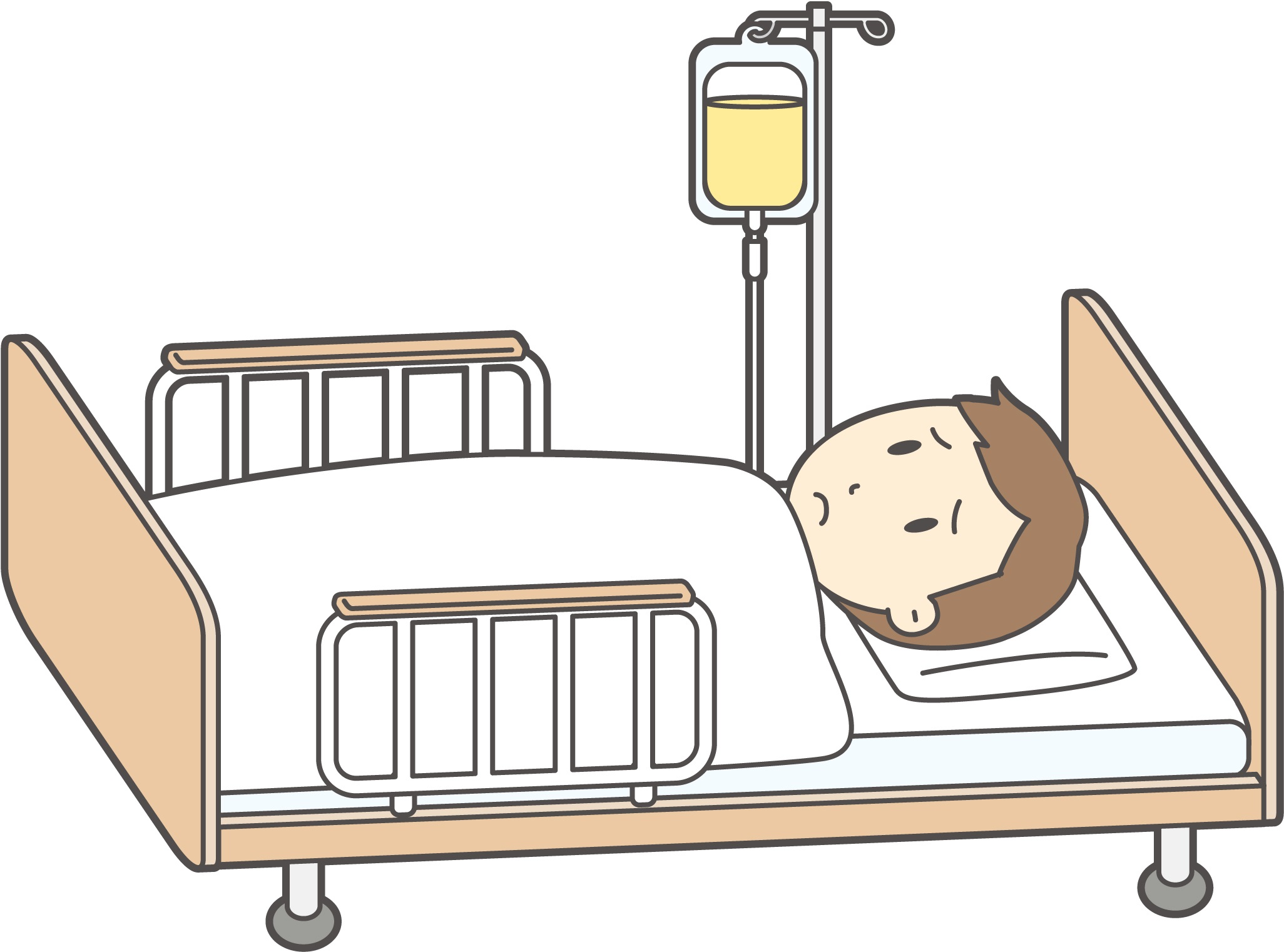おはようございます。
JMR協会の堀です。

医療療養病棟は
医療区分2・3の割合が高いほど、
評価される仕組みが導入されます。
直近の診療報酬改定でも
同様の傾向でした。
今回は、
より医療区分割合が
厳格化されることにってます。
そのため、
医療療養病棟の重症化が
さらに進むことは確実と思います。
そのため、
医療療養病棟における
リハビリテーションでは、
急性期や回復期と異なり、
呼吸・循環、褥瘡、摂食嚥下、
移動介助、排泄への対応が
セラピストに求められます。
また、医療療養病棟の患者は、
疾患別リハビリテーションの
算定上限日数を超えており、
医師からの改善の見込みの判断が
得られないことが多いです。
そのため、
月13単位以下でリハビリテーションを
提供しなくてはなりません。
本当に、
厳しい状況ですよね。
看護師や看護助手との
多職種連携が極めて重要となっています。
医療療養病棟における
リハビリテーションでは
心身機能を改善させることだけに
注目するのではなく、
呼吸、循環、嚥下、排泄というQOLに
最大限配慮する姿勢が求められると言えます。
各病棟の経営や運営を円滑にするためには、
セラピストの能力開発が極めて重要です。
2018年度診療報酬改定ではより、
アウトカム志向が強くなっており、
組織として様々なイノベーションに
取り組まなければなりません。
言うまでもなく、
イノベーションの源泉は人材と言えるでしょう!
2018年度診療報酬改定の
算定項目の理解を通じて、
どのような人材を育成するべきか?
を真摯に考える必要があり、
また、人材育成には時間がかかるため、
短期的な利益志向ではなく、
長期的な利益志向の下、
セラピストの人材育成を
行う姿勢が各医療機関には求められます。
非常に難しいと言えますが・・・。
私見的な意見であり、
独断と偏見で発しています。
療養、もしくは訪問へ流れるリハビリの人は
家庭>仕事
生活>仕事
の人が多いです。
そこで、どこまで一生懸命にできるのか?
4時半から詰め所でお話しているセラピストに対して・・。
どうすればよいのか?
そこを考えるべきじゃないかと思います。
協会に興味がある方は
是非、こちらをクリックして
お問い合わせ下さい!
お待ちしてま~~す笑