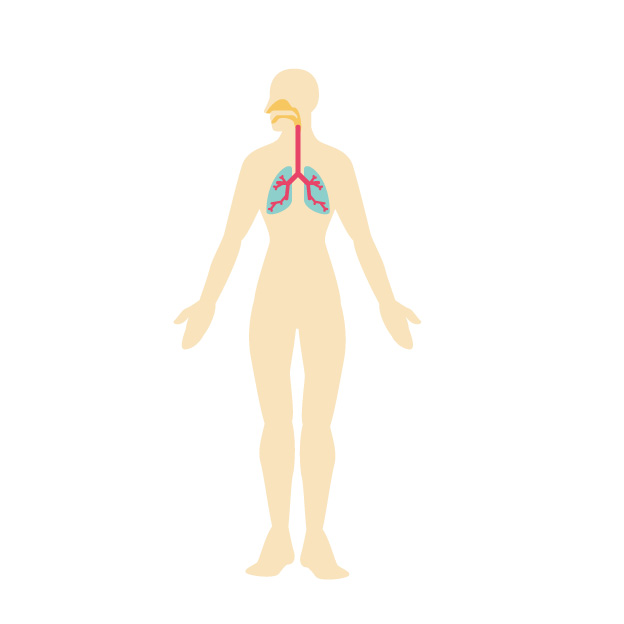おはようございます。
役員の井尻です。
呼吸シリーズ第2回目です。
今日は胸郭と胸腔について書こうと思います。
言葉の意味理解できていますか?
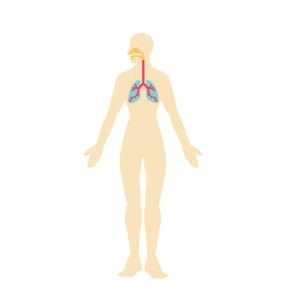
胸郭と横隔膜によって形成される体腔を胸腔と呼びます。
胸郭は縦隔によって左右に分けられています。
壁側胸膜と背側胸膜とは肺門でお互いに移行しており閉鎖された空間であり、胸膜腔を形成しています。
10~12mLの胸水が存在しており、壁側胸膜と肺側胸膜とは少量の胸水を挟みあって存在します。
胸腔内は常に陰圧であり、虚脱するのを防いでいます。
安静時吸気時で-4~-8cmH₂O、吸気時で-2~4cmH₂Oです。
しかし、努力的な呼吸運動では吸気時-40cmH₂Oとなり、呼気時40cmH₂Oになります。
呼吸運動は横隔膜と胸郭ならびに胸壁の筋肉の収縮により胸腔内圧を変化させています。
肋骨は後方で肋骨頭関節と肋横突関節をなし、弓状に斜め前下方に向かい前方で肋軟骨となって胸骨と接着しています。
吸気時に胸腔は水平横断面とともに上下方向に拡大し、胸腔内の陰圧が増強して肺が膨張します。
【まとめ】
今回を読めばなぜ肺が虚脱しないか理解できたと思います。
陰圧が大きなポイントでしたね!
陰圧が増加すると肺が膨張する仕組みになっているのです。
なんだか不思議な感じがしますね。