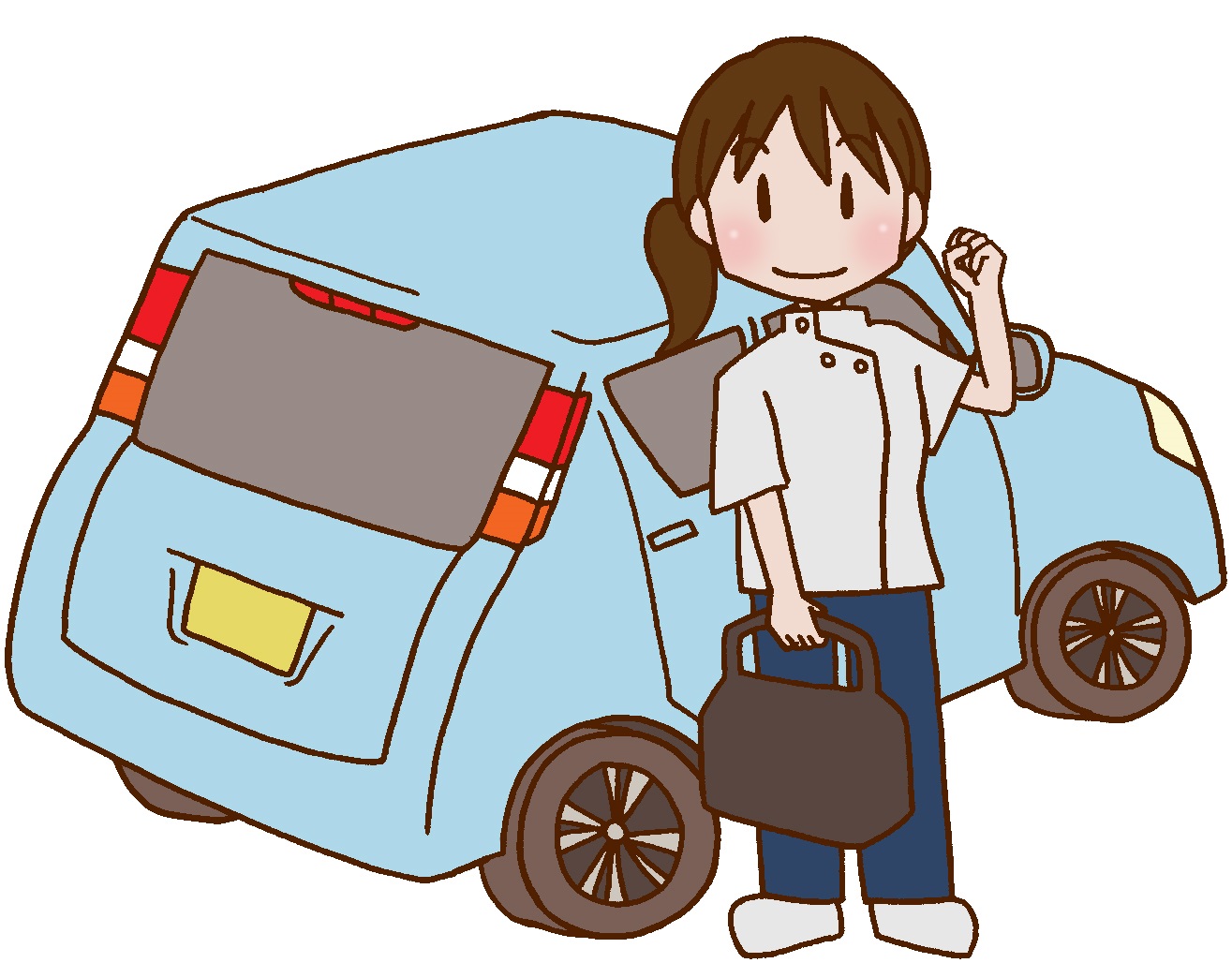おはようございます。
JMR協会の堀です。

僕自身、現在は、
『治療院』と『セミナー事業』、
『生活期(訪問リハビリ:雇われ)』
の仕事をしています。
治療院経営は、
正直大変です。
壁となるのは、
『マーケティング』と『自由診療』の2つです。
リハビリ業界は、
ビジネス業界では、
国からのお墨付きのある事業です。
介護事業はビックビジネスです。
その証拠に、有名な起業も入ってきていますね。
今回、
お伝えしたい事は、
訪問事業の現状です。
興味のある方は、
ご覧になってください。
リハビリテーションの花形市場とは?
今後、リハビリテーションの花形事業とは、
『訪問リハビリテーション』と
『通所リハビリテーション』であると、
僕自身考えています。
2018年度介護報酬改定を見てみると、
訪問リハビリテーションと
通所リハビリテーションにとって
大きな転換点ではないかと思っています。
リハビリテーションマネジメント加算が、
「4分類」され、
医師の関わり方が濃厚になればなるほど、
評価が上がっていく仕組みになっています。
例えば、
医師の関わり方を単に医師が書類を作成する、
医師が会議に参加するなどです。
それにより、「加算」になるという事です。
なぜ?そんな事になったのか?(持論)
自分なりに考えてみました。
訪問看護ステーション、訪問リハビリにおいて、
どうしても利益目的で、
訪問リハビリの件数を多くなりがちの
ステーションが多いです。
仕方がありませんが笑
損益&セラピスト自体のモチベーションも
関係していると思っています。
社会では、損益の事がメインですが・・・・。
「やる気」の問題も現場にはあります。
5時チンで帰りたいナース、
あまり仕事量をこなしたくないナースが
いるのも事実です。
そんな中、医師の関わりが薄いのも現実にあります。
入院、外来でのフォロー、どうしても適当とはいいませんが、
患者さんとの関わりが薄くなり、ナース・リハビリ任せになっている分があると思います。
現に、現状の患者さんの状態を
ちゃんと理解しせいる医者がどれだけいるのか?
今、何のリハビリをして、
何を目的に頑張っているか?
理解している医者はどれだけいるか?
すくないでしょう!
国が進める組織のチーム・地域でのチーム
医師が本気で訪問リハビリテーションや
通所リハビリテーションに関わっていくことを
実現するためには、組織のチームワーク、
リハビリテーションの質、人材育成、
医師やセラピストの採用などの
組織運営全体の改善が必要ではないかと思います。
厚生労働省はこのような改善を通じて、
『質の高い訪問リハビリテーション』や
『通所リハビリテーションの事業所』を
求めていると思います。
なぜならば、
今までの訪問リハビリテーションや
通所リハビリテーションは、
セラピストに運営を丸投げであり、
医者主導が弱かったと考えています。
また、
訪問リハビリテーションと
通所リハビリテーションでは、
要支援者へのリハビリテーションマネジメント加算、
生活行為向上リハビリテーション実施加算が認められた。
このことは、
非常に大きな意味を持つと思っています。
以前より財務省は、
訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・訪問看護ステーションにおける要支援者へのサービスは新総合事業へ移行することを求めており、2025年までに要支援者の新総合事業への移行が検討されていた。しかし、今回、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションにおいて要支援が評価されたことにより近い将来における新総合事業への移行の可能性は極めて低くなったと考えられる。ただ、要支援者に対して漫然とリハビリテーションを行うのではなく、期間限定で卒業を目的としたリハビリテーションが重要となってくるだろう。
協会に興味がある方は
是非、こちらをクリックして
お問い合わせ下さい!
お待ちしてま~~す笑